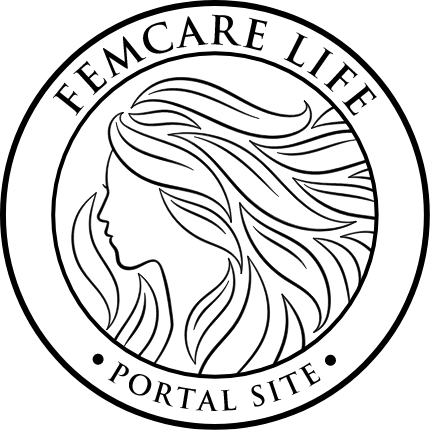フェムケアマガジン冷え性

冷え性を悪化させないための夏の過ごし方【温活美容家 おぬまあすかさん】
みなさんこんにちは、 温活美容家のおぬまあすかです。 寒暖差の激しい毎日が続いていますね。 しかし日中は暑い夏のような気温の日もあり、そろそろ夏冷え対策をはじめる季節となりました。 今回は皆さんに【冬の冷え性を悪化させないための夏の過ごし方】をご紹介させて頂きます。 暑い夏に体を冷やすことばかりをしてしまうと、寒い冬にしわ寄せとして、冷え性がひどくでてしまいます。ですので寒い季節に冷え性で悩まない為にも、実は夏の過ごし方って凄く大切となります。 冬の冷え性を悪化させないための夏の過ごし方とは? 暖かくなる夏の時期は “冷えとは無関係” と思いがちなんですが、今の時代はガンガンに冷えた冷房の部屋やシャワーなどの入浴の短縮により、夏でも冷えを感じやすく年中、冷え性に悩む方も少なくはないです。実は夏は冬よりも代謝が下がりやすくなります。 というのも、寒い冬は体が熱を生み出す為に頑張って脂肪や糖を代謝し熱を作り出してくれます。 しかし体温と同じ気温が続く夏は、熱を生み出さなくても大丈夫なので、代謝が下がりやすくなってしまいます。 夏の過ごし方によって、冬の冷え性にも影響するのでそんな代謝が下がり やすい夏だからこそ、夏の温活を意識し生活することで、冬の冷え性を軽減 することに繋がります。 温活をはじめてから年中温活を意識している私ですが、夏の温活として特に 気をつけている 【夏冷え対策】 を5つご紹介です。 ①冷房で冷えた室内では生足は厳禁! 夏の暑い日であっても室内では必ずストッキングやスパッツを履くことで冷房からの冷えを防いでいます。 ②下半身の冷えやむくみを感じる時は夏でもホッカイロを! 冷房でキンキンに冷えた室内に居て、体が冷えや浮腫みを感じる際は、お腹周りや腰のあたりにホッカイロを貼るだけで冷えが緩和されます。 また冷えによりお腹の調子が悪い時もホッカイロを貼っています。夏でも仕事場にはホッカイロを常備しています。 ③冷えを感じた際に羽織れるものを持ち歩く! 直接冷房に当たらない対策を日頃からすることで冷え性を悪化させることを防ぐことに繋がります。 冷たい風が直接肌に当たるとすごく体を冷やしてしまいますので、なるべく長時間冷房の室内にいる際は、何か軽く羽織れるものがあると冷え対策につながります。 ④冷えた室内では冷たい飲み物ではなく常温か温かい飲み物を! 寒い室内で冷たい飲み物を摂ることは、冷えや体の巡りを悪化させてしまいます。 温かい飲み物で体の内部から温めることで冷えの緩和に繋がるのでオススメです。夏の暑い日に温かな飲み物を飲むことが苦手な方は、常温の飲み物を飲むようにしましょう。...
冷え性を悪化させないための夏の過ごし方【温活美容家 おぬまあすかさん】
みなさんこんにちは、 温活美容家のおぬまあすかです。 寒暖差の激しい毎日が続いていますね。 しかし日中は暑い夏のような気温の日もあり、そろそろ夏冷え対策をはじめる季節となりました。 今回は皆さんに【冬の冷え性を悪化させないための夏の過ごし方】をご紹介させて頂きます。 暑い夏に体を冷やすことばかりをしてしまうと、寒い冬にしわ寄せとして、冷え性がひどくでてしまいます。ですので寒い季節に冷え性で悩まない為にも、実は夏の過ごし方って凄く大切となります。 冬の冷え性を悪化させないための夏の過ごし方とは? 暖かくなる夏の時期は “冷えとは無関係” と思いがちなんですが、今の時代はガンガンに冷えた冷房の部屋やシャワーなどの入浴の短縮により、夏でも冷えを感じやすく年中、冷え性に悩む方も少なくはないです。実は夏は冬よりも代謝が下がりやすくなります。 というのも、寒い冬は体が熱を生み出す為に頑張って脂肪や糖を代謝し熱を作り出してくれます。 しかし体温と同じ気温が続く夏は、熱を生み出さなくても大丈夫なので、代謝が下がりやすくなってしまいます。 夏の過ごし方によって、冬の冷え性にも影響するのでそんな代謝が下がり やすい夏だからこそ、夏の温活を意識し生活することで、冬の冷え性を軽減 することに繋がります。 温活をはじめてから年中温活を意識している私ですが、夏の温活として特に 気をつけている 【夏冷え対策】 を5つご紹介です。 ①冷房で冷えた室内では生足は厳禁! 夏の暑い日であっても室内では必ずストッキングやスパッツを履くことで冷房からの冷えを防いでいます。 ②下半身の冷えやむくみを感じる時は夏でもホッカイロを! 冷房でキンキンに冷えた室内に居て、体が冷えや浮腫みを感じる際は、お腹周りや腰のあたりにホッカイロを貼るだけで冷えが緩和されます。 また冷えによりお腹の調子が悪い時もホッカイロを貼っています。夏でも仕事場にはホッカイロを常備しています。 ③冷えを感じた際に羽織れるものを持ち歩く! 直接冷房に当たらない対策を日頃からすることで冷え性を悪化させることを防ぐことに繋がります。 冷たい風が直接肌に当たるとすごく体を冷やしてしまいますので、なるべく長時間冷房の室内にいる際は、何か軽く羽織れるものがあると冷え対策につながります。 ④冷えた室内では冷たい飲み物ではなく常温か温かい飲み物を! 寒い室内で冷たい飲み物を摂ることは、冷えや体の巡りを悪化させてしまいます。 温かい飲み物で体の内部から温めることで冷えの緩和に繋がるのでオススメです。夏の暑い日に温かな飲み物を飲むことが苦手な方は、常温の飲み物を飲むようにしましょう。...

温活初心者さんにおすすめ!冬の冷え症対策アイテム【温活美容家 おぬまあすかさん】
みなさんこんにちは、温活美容家のおぬまあすかです。すっかりと冬らしく寒い季節となりましたね。今年は暑い日が長い期間続いており、いきなり寒くなってしまったので、体調を崩しやすい方も多いみたいですので、みなさんもお身体にはお気をつけてお過ごしくださいね。今回はすっかり寒くなってきましたので、温活初心者さんにおすすめな冬の冷え症対策アイテムをご紹介させて頂きます。温活には取り組んでみたいけれど、何からはじめたらいいの?何を揃えたらいいの?何が温活に繋がるの?なんていう温活初心者さんは良かったらご参考になさってみてくださいね。 冷えは大敵! まず私は温活をはじめて3年以上になるのですが、温活をはじめてから当時35℃前半だった基礎体温が+1℃上がり、体重は−20㎏の減量に成功し、多少の体重の上下はあるのですが、現在は大きなリバウンドもなく沢山の身体の不調も改善されました!体温が上がることが、体にとってこんなにもメリットが沢山あるんだなぁ…と、温活をはじめて以来気付きと学びの毎日です。今より20kg近く太っていた当時の私は、・体の冷えには無関心・体の不調にも無関心冬でも体を冷やさない対策なんてしないので冷え症は悪化する一方で、基礎体温は低くなり代謝は落ちるばかりでした。冷えを解消することによって起こるメリットは沢山です!・身体の老廃物を外に排出する為にも・美容のためにも・痩せ体質になるダイエットにも温活は一番の近道となります。冷えは綺麗になる為には大敵!だと自身の体験から学びました。 温活初心者さんにおすすめ!冷え症対策アイテム 温活初心者さんの冬の冷え症対策アイテムにおすすめなのがホッカイロ!です。ホッカイロは手ごろな価格で、コンビニやドラックストアなどで身近で手に入りやすいですよね。私の場合は冬に限らず、夏の冷房で寒い室内の中でも大活躍なので、職場のロッカーには常備しています。また女性であれば、生理期間中の体温が下がる期間にもホッカイロは役立ちますよ。 ホッカイロの効果的な使い方は? ホッカイロといってもどこの部位に貼るかによって効果が変わってきます。その時々のご自身の体調と向き合いながら、貼る部位を工夫しましょう。 ◯おへそ周りに貼る ・疲れを感じるときや、疲れがなかなかとれないとき・生理痛がつらく感じるとき・手足の末端部分の冷えを強く感じるとき・便秘やお腹の冷えを感じるとき ◯腰回りに貼る ・お尻周りを触った時に冷えてこり固まっているとき・腰痛がひどいとき・お腹の張りや便秘がきになるとき ◯背中の上部に貼る ・呼吸が浅く巡りを悪く感じるとき・肩こりがひどいとき・疲れがとりづらいとき ◯足裏に貼る ・足先の冷えが気になるとき・脚の浮腫みがひどいとき このようにホッカイロの貼る場所によって効果的に体を温められるので、温活につながります。私も日頃から自分の冷えてる部分を意識しながら、ホッカイロを活用しているので、みなさんも良かったらご参考になさってみて下さいね。これからますます寒さが本格的となり、体の冷えを感じやすくなるかと思いますが、一緒に楽しみながら温活をして今年の冬を乗り越えていきましょう。 AUTHOR おぬま あすか PROFILE 温活美容家。 “美容を通して人を笑顔に豊かに幸せに”がモットー。 数々のダイエットに挑戦してはリバウンド・体調不良を繰り返した経験から、体温を上げるこ とを意識した温活ダイエットにたどりつく。 自身の経験を『ゆるぽか美活』としてインスタグラムやブログで発信中。多くの女性から支持を集めている。 MORE INFO 温活美容家🌸おぬまあすか 【代謝を上げて太りにくい体質へ】 Instagram...
温活初心者さんにおすすめ!冬の冷え症対策アイテム【温活美容家 おぬまあすかさん】
みなさんこんにちは、温活美容家のおぬまあすかです。すっかりと冬らしく寒い季節となりましたね。今年は暑い日が長い期間続いており、いきなり寒くなってしまったので、体調を崩しやすい方も多いみたいですので、みなさんもお身体にはお気をつけてお過ごしくださいね。今回はすっかり寒くなってきましたので、温活初心者さんにおすすめな冬の冷え症対策アイテムをご紹介させて頂きます。温活には取り組んでみたいけれど、何からはじめたらいいの?何を揃えたらいいの?何が温活に繋がるの?なんていう温活初心者さんは良かったらご参考になさってみてくださいね。 冷えは大敵! まず私は温活をはじめて3年以上になるのですが、温活をはじめてから当時35℃前半だった基礎体温が+1℃上がり、体重は−20㎏の減量に成功し、多少の体重の上下はあるのですが、現在は大きなリバウンドもなく沢山の身体の不調も改善されました!体温が上がることが、体にとってこんなにもメリットが沢山あるんだなぁ…と、温活をはじめて以来気付きと学びの毎日です。今より20kg近く太っていた当時の私は、・体の冷えには無関心・体の不調にも無関心冬でも体を冷やさない対策なんてしないので冷え症は悪化する一方で、基礎体温は低くなり代謝は落ちるばかりでした。冷えを解消することによって起こるメリットは沢山です!・身体の老廃物を外に排出する為にも・美容のためにも・痩せ体質になるダイエットにも温活は一番の近道となります。冷えは綺麗になる為には大敵!だと自身の体験から学びました。 温活初心者さんにおすすめ!冷え症対策アイテム 温活初心者さんの冬の冷え症対策アイテムにおすすめなのがホッカイロ!です。ホッカイロは手ごろな価格で、コンビニやドラックストアなどで身近で手に入りやすいですよね。私の場合は冬に限らず、夏の冷房で寒い室内の中でも大活躍なので、職場のロッカーには常備しています。また女性であれば、生理期間中の体温が下がる期間にもホッカイロは役立ちますよ。 ホッカイロの効果的な使い方は? ホッカイロといってもどこの部位に貼るかによって効果が変わってきます。その時々のご自身の体調と向き合いながら、貼る部位を工夫しましょう。 ◯おへそ周りに貼る ・疲れを感じるときや、疲れがなかなかとれないとき・生理痛がつらく感じるとき・手足の末端部分の冷えを強く感じるとき・便秘やお腹の冷えを感じるとき ◯腰回りに貼る ・お尻周りを触った時に冷えてこり固まっているとき・腰痛がひどいとき・お腹の張りや便秘がきになるとき ◯背中の上部に貼る ・呼吸が浅く巡りを悪く感じるとき・肩こりがひどいとき・疲れがとりづらいとき ◯足裏に貼る ・足先の冷えが気になるとき・脚の浮腫みがひどいとき このようにホッカイロの貼る場所によって効果的に体を温められるので、温活につながります。私も日頃から自分の冷えてる部分を意識しながら、ホッカイロを活用しているので、みなさんも良かったらご参考になさってみて下さいね。これからますます寒さが本格的となり、体の冷えを感じやすくなるかと思いますが、一緒に楽しみながら温活をして今年の冬を乗り越えていきましょう。 AUTHOR おぬま あすか PROFILE 温活美容家。 “美容を通して人を笑顔に豊かに幸せに”がモットー。 数々のダイエットに挑戦してはリバウンド・体調不良を繰り返した経験から、体温を上げるこ とを意識した温活ダイエットにたどりつく。 自身の経験を『ゆるぽか美活』としてインスタグラムやブログで発信中。多くの女性から支持を集めている。 MORE INFO 温活美容家🌸おぬまあすか 【代謝を上げて太りにくい体質へ】 Instagram...

夏バテ予防な夏冷え対策な温活たれレシピ【温活美容家 おぬまあすかさん】
みなさんこんにちは、 温活美容家のおぬまあすかです。梅雨真っ只中ですが、 例年に比べて暑い日が続いておりますね。 湿度も高く暑さがより厳しく感じる毎日ですので、皆さんもどうぞ お体にはお気をつけてお過ごしくださいね。そしていきなり暑くなったことで、キンキンに冷えた冷たい飲み物 や冷たい食べ物を過度に欲してしまい食欲が落ちて夏バテっぽくなってきていたり、外と室内の温度差や冷房による身体の疲れで、食欲 が落ちてしまう方も少なくないと思います。そんなこの時期の疲れを放っておくと、冷えに限らず様々な身体の 不調を招いてしまいます。それらの不調を防ぐためにも大活躍な、簡単夏の温活レシピのご紹 介させていただきます。今回は夏バテなどで食欲がないときにでも美味しく食べて頂ける、お蕎麦やそうめんにつけると美味しいタレのレシピです。また夏冷え対策にも繋がる温活レシピですので、・体の疲れが取れづらく感じている方・冷房のかかった部屋で手先の冷えを感じる方・夏に生理痛がひどくなってしまい方・体調がなんだか優れない方などにオススメです。また普段のお蕎麦のシンプルな食べ方に飽きてしまった方にももち ろんオススメです。私自身も夏はすごく好きな季節なんですが、 毎年冷房に体が慣れづ に不調を何回か繰り返してしまいます。ですので、 夏の冷え対策をしっかりとしつつ、この温活レシピは夏の間に何十回とリピートして作って食べているお気に入りなんです! 【夏こそ冷え対策をしよう】 夏に体を冷やしすぎると冬の冷え性がよりつらく感じてしまい、夏 の冷えは冬に影響してしまうからこそ、夏の冷え対策って実はすご く大切なんです。温活のひとつとして「旬の食材を楽しむ」ということがあります。 夏野菜は夏に体温を下げる大事な働きをしてくれますが、 生サラダ で食べ過ぎると、日頃から冷房や冷たい飲みものの飲み過ぎで冷え 体質の人はより冷え体質となり、体の巡りを悪化させてしまいます。そんな冷え体質の方は、 体を温める働きのある食材と夏野菜を組み 合わせて食べたり、熱を通してから食べたりと、体を冷やしすぎな いように意識してみることで冷え対策にもつながります。 【夏冷え対策な温活たれレシピ】 まず具材はお好みで、 季節の野菜を中心に選ぶのがオススメです。 私がお気に入りなのは、なす、ズッキーニ、トマト、などが好きで す。きのこ類を入れてもすごく美味しいです。お好みの野菜と一緒にお肉も入れるとコクが出てより食べ応えが出ます。これらの具材を先にごま油で炒めて、 めんつゆを入れて上記の味付...
夏バテ予防な夏冷え対策な温活たれレシピ【温活美容家 おぬまあすかさん】
みなさんこんにちは、 温活美容家のおぬまあすかです。梅雨真っ只中ですが、 例年に比べて暑い日が続いておりますね。 湿度も高く暑さがより厳しく感じる毎日ですので、皆さんもどうぞ お体にはお気をつけてお過ごしくださいね。そしていきなり暑くなったことで、キンキンに冷えた冷たい飲み物 や冷たい食べ物を過度に欲してしまい食欲が落ちて夏バテっぽくなってきていたり、外と室内の温度差や冷房による身体の疲れで、食欲 が落ちてしまう方も少なくないと思います。そんなこの時期の疲れを放っておくと、冷えに限らず様々な身体の 不調を招いてしまいます。それらの不調を防ぐためにも大活躍な、簡単夏の温活レシピのご紹 介させていただきます。今回は夏バテなどで食欲がないときにでも美味しく食べて頂ける、お蕎麦やそうめんにつけると美味しいタレのレシピです。また夏冷え対策にも繋がる温活レシピですので、・体の疲れが取れづらく感じている方・冷房のかかった部屋で手先の冷えを感じる方・夏に生理痛がひどくなってしまい方・体調がなんだか優れない方などにオススメです。また普段のお蕎麦のシンプルな食べ方に飽きてしまった方にももち ろんオススメです。私自身も夏はすごく好きな季節なんですが、 毎年冷房に体が慣れづ に不調を何回か繰り返してしまいます。ですので、 夏の冷え対策をしっかりとしつつ、この温活レシピは夏の間に何十回とリピートして作って食べているお気に入りなんです! 【夏こそ冷え対策をしよう】 夏に体を冷やしすぎると冬の冷え性がよりつらく感じてしまい、夏 の冷えは冬に影響してしまうからこそ、夏の冷え対策って実はすご く大切なんです。温活のひとつとして「旬の食材を楽しむ」ということがあります。 夏野菜は夏に体温を下げる大事な働きをしてくれますが、 生サラダ で食べ過ぎると、日頃から冷房や冷たい飲みものの飲み過ぎで冷え 体質の人はより冷え体質となり、体の巡りを悪化させてしまいます。そんな冷え体質の方は、 体を温める働きのある食材と夏野菜を組み 合わせて食べたり、熱を通してから食べたりと、体を冷やしすぎな いように意識してみることで冷え対策にもつながります。 【夏冷え対策な温活たれレシピ】 まず具材はお好みで、 季節の野菜を中心に選ぶのがオススメです。 私がお気に入りなのは、なす、ズッキーニ、トマト、などが好きで す。きのこ類を入れてもすごく美味しいです。お好みの野菜と一緒にお肉も入れるとコクが出てより食べ応えが出ます。これらの具材を先にごま油で炒めて、 めんつゆを入れて上記の味付...

【隠れズボラ女子がお伝えする】季節の変わり目に役立つ温活術!
だんだんと夏本番に向けて暑くなってきてきましたね。季節の変わり目は、朝晩の温度差が激しく気圧の変化もあるので体調不良になる方も多いですよね。 なんだか調子が良くない、でもやることはやらなけれならない状況… そんな季節の変わり目を乗り越える温活を活かした方法をご紹介していきます!①夏の冷え対策レシピ②香りで自律神経整える③1年中使える服装の対策暑い時期に入ると、食欲も減退気味に陥りやすい… そんな時に「普段の食事にプラス1品」するだけで冷えの対策にもなるレシピを紹介します! ①夏の冷え対策レシピ ▼ニラ玉もやし炒め 〈材料〉 ・ニラ 1/2袋・もやし 1/2袋・にんにく 1片・卵 2個・鷹の爪 1本A 砂糖 大さじ1A 塩 少々B オイスターソース 大さじ1B 醤油 小さじ1・ごま油 大さじ1・胡椒 少々 〈作り方〉 ①ニラは6頭分くらいに切り、にんにくをみじん切って、鷹の爪を小口切りにする。②卵を溶きほぐしAの砂糖、塩を入れる。③フライパンに半分のごま油を入れて、強火にし卵を入れて10秒ほど混ぜて一度別のお皿に取り出しておく。④フライパンに残りのごま油を入れてにんにく、鷹の爪を入れて弱火で炒め香りがたったら強火にしてもやしを入れる。⑤❹にBのオイスターソースと醤油とニラを加えて少し火を止めて❸の卵と胡椒を混ぜ合わせ器に盛って完成! ▼食材の栄養やレシピの食べ方活用方法 夏に食べるべき冷え対策食材のニラ!ニラには血流を良くし、身体を温める働きがあると言われています。 もやしには、エネルギー代謝に欠かせないビタミンB1やビタミンB2、免疫力を高める効果のあるといわれているビタミンC、高血圧予防効果的なカリウムなどが豊富に含まれています。にんにくには、疲労回復やカラダを活性化してくれる強壮作用があるので元気になりたい時にも最適です。 普段のご飯にも取り入れやすく、少し多めに作っておいてお弁当のおかずに入れてもOK! ※お弁当の時は、少しニンニクを減らして作ると匂いも気になりずらいです。 ▼夏野菜ポテトサラダ 〈材料〉 じゃがいも 2個ズッキーニ 1本にんじん 50gツナ缶 1缶大葉 5枚オリーブオイル 大さじ1塩 少々ブラックペッパー 少々A塩麹 20gA穀物酢 30g 〈作り方〉 ① じゃがいもは水で洗い、皮に十字に切り込みをいれて濡らしたキッチンペーパーで包み、ラップでくるむ。じゃがいも1個につき電子レンジで600Wで4分加熱し、熱いうちに皮をむき、スプーンなどでつぶす。②ズッキーニは1cmくらいの輪切り、にんじんは8mmくらいの角切りにし、フライパンにオリーブオイルをひいて焼いて焼き色がついたら塩とブラックペッパーを少々ふる。③ 大葉は千切りにする。④Aの塩麹・穀物酢は混ぜ合わせておく。⑤つぶしたじゃがいもにツナ缶と焼いたズッキーニとにんじんを入れ、混ぜ合わせたAの調味料も和える。⑥最後に、千切りにした大葉をのせて完成! ▼食材の栄養やレシピの食べ方活用方法 にんじん、じゃがいもは陽の食べ物と言われていて身体をあたためてくれる食べ物です!積極的に摂取することでカラダの内側からの温活になります。 また、このレシピに使う野菜には他にも嬉しい効果がたくさんあります。...
【隠れズボラ女子がお伝えする】季節の変わり目に役立つ温活術!
だんだんと夏本番に向けて暑くなってきてきましたね。季節の変わり目は、朝晩の温度差が激しく気圧の変化もあるので体調不良になる方も多いですよね。 なんだか調子が良くない、でもやることはやらなけれならない状況… そんな季節の変わり目を乗り越える温活を活かした方法をご紹介していきます!①夏の冷え対策レシピ②香りで自律神経整える③1年中使える服装の対策暑い時期に入ると、食欲も減退気味に陥りやすい… そんな時に「普段の食事にプラス1品」するだけで冷えの対策にもなるレシピを紹介します! ①夏の冷え対策レシピ ▼ニラ玉もやし炒め 〈材料〉 ・ニラ 1/2袋・もやし 1/2袋・にんにく 1片・卵 2個・鷹の爪 1本A 砂糖 大さじ1A 塩 少々B オイスターソース 大さじ1B 醤油 小さじ1・ごま油 大さじ1・胡椒 少々 〈作り方〉 ①ニラは6頭分くらいに切り、にんにくをみじん切って、鷹の爪を小口切りにする。②卵を溶きほぐしAの砂糖、塩を入れる。③フライパンに半分のごま油を入れて、強火にし卵を入れて10秒ほど混ぜて一度別のお皿に取り出しておく。④フライパンに残りのごま油を入れてにんにく、鷹の爪を入れて弱火で炒め香りがたったら強火にしてもやしを入れる。⑤❹にBのオイスターソースと醤油とニラを加えて少し火を止めて❸の卵と胡椒を混ぜ合わせ器に盛って完成! ▼食材の栄養やレシピの食べ方活用方法 夏に食べるべき冷え対策食材のニラ!ニラには血流を良くし、身体を温める働きがあると言われています。 もやしには、エネルギー代謝に欠かせないビタミンB1やビタミンB2、免疫力を高める効果のあるといわれているビタミンC、高血圧予防効果的なカリウムなどが豊富に含まれています。にんにくには、疲労回復やカラダを活性化してくれる強壮作用があるので元気になりたい時にも最適です。 普段のご飯にも取り入れやすく、少し多めに作っておいてお弁当のおかずに入れてもOK! ※お弁当の時は、少しニンニクを減らして作ると匂いも気になりずらいです。 ▼夏野菜ポテトサラダ 〈材料〉 じゃがいも 2個ズッキーニ 1本にんじん 50gツナ缶 1缶大葉 5枚オリーブオイル 大さじ1塩 少々ブラックペッパー 少々A塩麹 20gA穀物酢 30g 〈作り方〉 ① じゃがいもは水で洗い、皮に十字に切り込みをいれて濡らしたキッチンペーパーで包み、ラップでくるむ。じゃがいも1個につき電子レンジで600Wで4分加熱し、熱いうちに皮をむき、スプーンなどでつぶす。②ズッキーニは1cmくらいの輪切り、にんじんは8mmくらいの角切りにし、フライパンにオリーブオイルをひいて焼いて焼き色がついたら塩とブラックペッパーを少々ふる。③ 大葉は千切りにする。④Aの塩麹・穀物酢は混ぜ合わせておく。⑤つぶしたじゃがいもにツナ缶と焼いたズッキーニとにんじんを入れ、混ぜ合わせたAの調味料も和える。⑥最後に、千切りにした大葉をのせて完成! ▼食材の栄養やレシピの食べ方活用方法 にんじん、じゃがいもは陽の食べ物と言われていて身体をあたためてくれる食べ物です!積極的に摂取することでカラダの内側からの温活になります。 また、このレシピに使う野菜には他にも嬉しい効果がたくさんあります。...

冷え性が便秘と痔の原因になることもある?相談できない女性の悩みを解消します
「痔」と聞くと男性の病気のように思われるかも知れませんが、実は女性にも多く、症状があらわれても恥ずかしさから治療せずに悪化してしまうこともあります。 痔になる原因はさまざまありますが、便秘やからだの冷えも原因のひとつといわれています。この記事では、痔について知ったうえで悪化させないための対策をご紹介していきます。だれにも相談できずに痔に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。 そもそも「痔」とはどんな病気? 痔とは、肛門や肛門周辺に起こる病気を指します。痔は症状によって3つの種類に分けられており、それぞれ原因や症状が異なります。 また痔は、3人に1人が発症すると言われるほど身近な病気ですが、女性は痔に対する恥ずかしさから、症状があらわれても放置して治癒が遅れることも…。原因や症状を知って少しでも早めに対策を行いましょう。 いぼ痔(痔核) いぼ痔は、肛門の内側にできる内痔核(ないじかく)と、肛門の外にできる外痔核(がいじかく)の2つの種類があります。痔の中ではいぼ痔がもっとも多く、痔を患っている方の約50%がいぼ痔と言われています。 内痔核は痛みがほとんどなく、排便時の出血でいぼ痔に気付く人が多いといわれています。また、内痔核が進行すると肛門の外へ飛び出したり、次第に指で押し戻しても戻らなくなったりすることも…。一方の外痔核は、腫れを伴って激しく痛みますが出血は少ないという特徴があります。 切れ痔(裂肛) 肛門の粘膜が裂けた状態が切れ痔です。切れ痔の原因は慢性的な下痢によるほか、便秘で固い便をいきんで出そうとする刺激で裂けることが多いです。 切れ痔を繰り返すと、裂け目に炎症が起きてポリープができ、肛門が狭くなることもあります。 痔ろう(あな痔) 肛門の組織が大腸菌などの細菌に感染すると、皮膚を破って直腸から1本のトンネルができる症状を痔ろうといいます。肛門付近の皮膚が腫れて激しい痛みが出るほか、発熱を伴うこともあります。できてしまったトンネルから膿が漏れるため、下着の汚れで痔ろうに気付く方が多いです。痔ろうは市販薬では治すことはできず、肛門専門医での治療を要します。 女性に多い痔になる原因とは? 痔になるのは男性より、むしろライフスタイルの変化や体質的に女性の方が痔になりやすいと言われています。ここでは女性に多い痔になる原因について見ていきましょう。 原因1:便秘 女性の痔の原因で多いのは便秘です。女性は男性に比べて腹筋が弱く、便を押し出す力がそもそも弱いのが便秘の原因のひとつです。 また、月経前は黄体ホルモンの影響で腸の動きが抑制されるうえ、黄体ホルモンの水分を体内にため込む作用により便が固くなり、出にくくなることも便秘の原因です。 さらに、過度なダイエットが便秘を招くこともあります。食事量が減ると便の量も減ってしまうためです。ダイエットをする場合は、カロリーを抑えつつ、便の量を増やすために食物繊維をしっかり摂るようにしましょう。 原因2:妊娠・出産 女性は妊娠から出産までの期間中、子宮が大きくなって肛門付近の血流が悪くなり痔になることがあります。また、出産は胎児を押し出すために強くいきむため、内痔核ができてしまうこともあります。 原因3:長時間のデスクワーク 座りっぱなしになりやすいデスクワークも痔の原因のひとつです。長時間同じ姿勢で座るデスクワークは、肛門周辺の血液循環を悪化させてしまいます。 肛門付近の血管は毛細血管が多いため、血流が悪くなるとうっ血した状態になりやすく、さらに血流が滞るという悪循環に陥ります。 原因4:体の冷え 体が冷えると、筋肉や血管の収縮により肛門周辺の血流も悪くなって痔ができやすい状態になります。 また、女性は男性よりホルモンバランスが乱れやすいため、体の冷えが起こりやすく、痔になりやすいといえます。 痔は、夏より血流が悪くなりやすい冬の発症が多いのも、痔と体の冷えが関係していることをあらわしているといえるでしょう。冷え性の方は特に夏の冷房の効きすぎにも注意しましょう。 痔を悪化させないための3つのセルフケア これまでお伝えしたように、さまざまな要因によって女性は男性より痔になりやすいといえます。しかし、生活習慣の改善や心がけで痔を防いだり、改善したりすることができます。...
冷え性が便秘と痔の原因になることもある?相談できない女性の悩みを解消します
「痔」と聞くと男性の病気のように思われるかも知れませんが、実は女性にも多く、症状があらわれても恥ずかしさから治療せずに悪化してしまうこともあります。 痔になる原因はさまざまありますが、便秘やからだの冷えも原因のひとつといわれています。この記事では、痔について知ったうえで悪化させないための対策をご紹介していきます。だれにも相談できずに痔に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。 そもそも「痔」とはどんな病気? 痔とは、肛門や肛門周辺に起こる病気を指します。痔は症状によって3つの種類に分けられており、それぞれ原因や症状が異なります。 また痔は、3人に1人が発症すると言われるほど身近な病気ですが、女性は痔に対する恥ずかしさから、症状があらわれても放置して治癒が遅れることも…。原因や症状を知って少しでも早めに対策を行いましょう。 いぼ痔(痔核) いぼ痔は、肛門の内側にできる内痔核(ないじかく)と、肛門の外にできる外痔核(がいじかく)の2つの種類があります。痔の中ではいぼ痔がもっとも多く、痔を患っている方の約50%がいぼ痔と言われています。 内痔核は痛みがほとんどなく、排便時の出血でいぼ痔に気付く人が多いといわれています。また、内痔核が進行すると肛門の外へ飛び出したり、次第に指で押し戻しても戻らなくなったりすることも…。一方の外痔核は、腫れを伴って激しく痛みますが出血は少ないという特徴があります。 切れ痔(裂肛) 肛門の粘膜が裂けた状態が切れ痔です。切れ痔の原因は慢性的な下痢によるほか、便秘で固い便をいきんで出そうとする刺激で裂けることが多いです。 切れ痔を繰り返すと、裂け目に炎症が起きてポリープができ、肛門が狭くなることもあります。 痔ろう(あな痔) 肛門の組織が大腸菌などの細菌に感染すると、皮膚を破って直腸から1本のトンネルができる症状を痔ろうといいます。肛門付近の皮膚が腫れて激しい痛みが出るほか、発熱を伴うこともあります。できてしまったトンネルから膿が漏れるため、下着の汚れで痔ろうに気付く方が多いです。痔ろうは市販薬では治すことはできず、肛門専門医での治療を要します。 女性に多い痔になる原因とは? 痔になるのは男性より、むしろライフスタイルの変化や体質的に女性の方が痔になりやすいと言われています。ここでは女性に多い痔になる原因について見ていきましょう。 原因1:便秘 女性の痔の原因で多いのは便秘です。女性は男性に比べて腹筋が弱く、便を押し出す力がそもそも弱いのが便秘の原因のひとつです。 また、月経前は黄体ホルモンの影響で腸の動きが抑制されるうえ、黄体ホルモンの水分を体内にため込む作用により便が固くなり、出にくくなることも便秘の原因です。 さらに、過度なダイエットが便秘を招くこともあります。食事量が減ると便の量も減ってしまうためです。ダイエットをする場合は、カロリーを抑えつつ、便の量を増やすために食物繊維をしっかり摂るようにしましょう。 原因2:妊娠・出産 女性は妊娠から出産までの期間中、子宮が大きくなって肛門付近の血流が悪くなり痔になることがあります。また、出産は胎児を押し出すために強くいきむため、内痔核ができてしまうこともあります。 原因3:長時間のデスクワーク 座りっぱなしになりやすいデスクワークも痔の原因のひとつです。長時間同じ姿勢で座るデスクワークは、肛門周辺の血液循環を悪化させてしまいます。 肛門付近の血管は毛細血管が多いため、血流が悪くなるとうっ血した状態になりやすく、さらに血流が滞るという悪循環に陥ります。 原因4:体の冷え 体が冷えると、筋肉や血管の収縮により肛門周辺の血流も悪くなって痔ができやすい状態になります。 また、女性は男性よりホルモンバランスが乱れやすいため、体の冷えが起こりやすく、痔になりやすいといえます。 痔は、夏より血流が悪くなりやすい冬の発症が多いのも、痔と体の冷えが関係していることをあらわしているといえるでしょう。冷え性の方は特に夏の冷房の効きすぎにも注意しましょう。 痔を悪化させないための3つのセルフケア これまでお伝えしたように、さまざまな要因によって女性は男性より痔になりやすいといえます。しかし、生活習慣の改善や心がけで痔を防いだり、改善したりすることができます。...

【世界的ファッション誌が認めた最新美容】ヘアドライヤーと美顔器が1台となった『SIVERS M...
全身に使える『次世代』光健康美容機器「SIVERS Magick」は、髪をいたわるヘアドライヤーと、フェイスラインの引き締め効果や肌弾力アップ効果などが期待できる美顔器の1台2役! お風呂上がりにいつものように髪を乾かすだけで、パサついた髪に潤いを与え、縮毛と乾燥、抜け毛を防ぎます。 また、遠赤外線×近赤外線×温風のトリプルアプローチにより肌の弾力性の向上や細胞を活性化。細胞を構成している分子そのものを活性化するため、髪だけではなく、頭皮や肌にも効果があります。 今回は、独自特許技術のまったく新しいリフト式美顔器ドライヤー、SIVERS Magick(シヴァーズマジック)の魅力をご紹介します。 SIVERS Magick(シヴァーズマジック)はこんな方におすすめ! ~美容が気になる女性に~ 乾いた髪に潤いを与えたい 傷んだ髪を修復したい 枝毛を減らしたい 肌のハリ・弾力を取り戻したい フェイスラインを引き締めたい ほうれい線を目立たなくしたい ~髪が気になる男性に~ 頭皮の脂っぽさが気になる 髪が弱くなったと思う 抜け毛が気になる ~ご年配の方に~ 首や肩のコリをなんとかしたい 体が冷えて夜眠れない 首まわりのシワが気になる ~ご家族全員に~ 手足の冷えをすぐに何とかしたい 体が冷えて、夜眠れない お腹周りが冷える 更年期でイライラする ストレスを軽減したい...
【世界的ファッション誌が認めた最新美容】ヘアドライヤーと美顔器が1台となった『SIVERS M...
全身に使える『次世代』光健康美容機器「SIVERS Magick」は、髪をいたわるヘアドライヤーと、フェイスラインの引き締め効果や肌弾力アップ効果などが期待できる美顔器の1台2役! お風呂上がりにいつものように髪を乾かすだけで、パサついた髪に潤いを与え、縮毛と乾燥、抜け毛を防ぎます。 また、遠赤外線×近赤外線×温風のトリプルアプローチにより肌の弾力性の向上や細胞を活性化。細胞を構成している分子そのものを活性化するため、髪だけではなく、頭皮や肌にも効果があります。 今回は、独自特許技術のまったく新しいリフト式美顔器ドライヤー、SIVERS Magick(シヴァーズマジック)の魅力をご紹介します。 SIVERS Magick(シヴァーズマジック)はこんな方におすすめ! ~美容が気になる女性に~ 乾いた髪に潤いを与えたい 傷んだ髪を修復したい 枝毛を減らしたい 肌のハリ・弾力を取り戻したい フェイスラインを引き締めたい ほうれい線を目立たなくしたい ~髪が気になる男性に~ 頭皮の脂っぽさが気になる 髪が弱くなったと思う 抜け毛が気になる ~ご年配の方に~ 首や肩のコリをなんとかしたい 体が冷えて夜眠れない 首まわりのシワが気になる ~ご家族全員に~ 手足の冷えをすぐに何とかしたい 体が冷えて、夜眠れない お腹周りが冷える 更年期でイライラする ストレスを軽減したい...